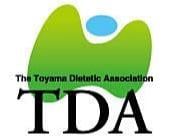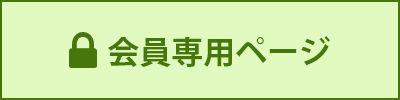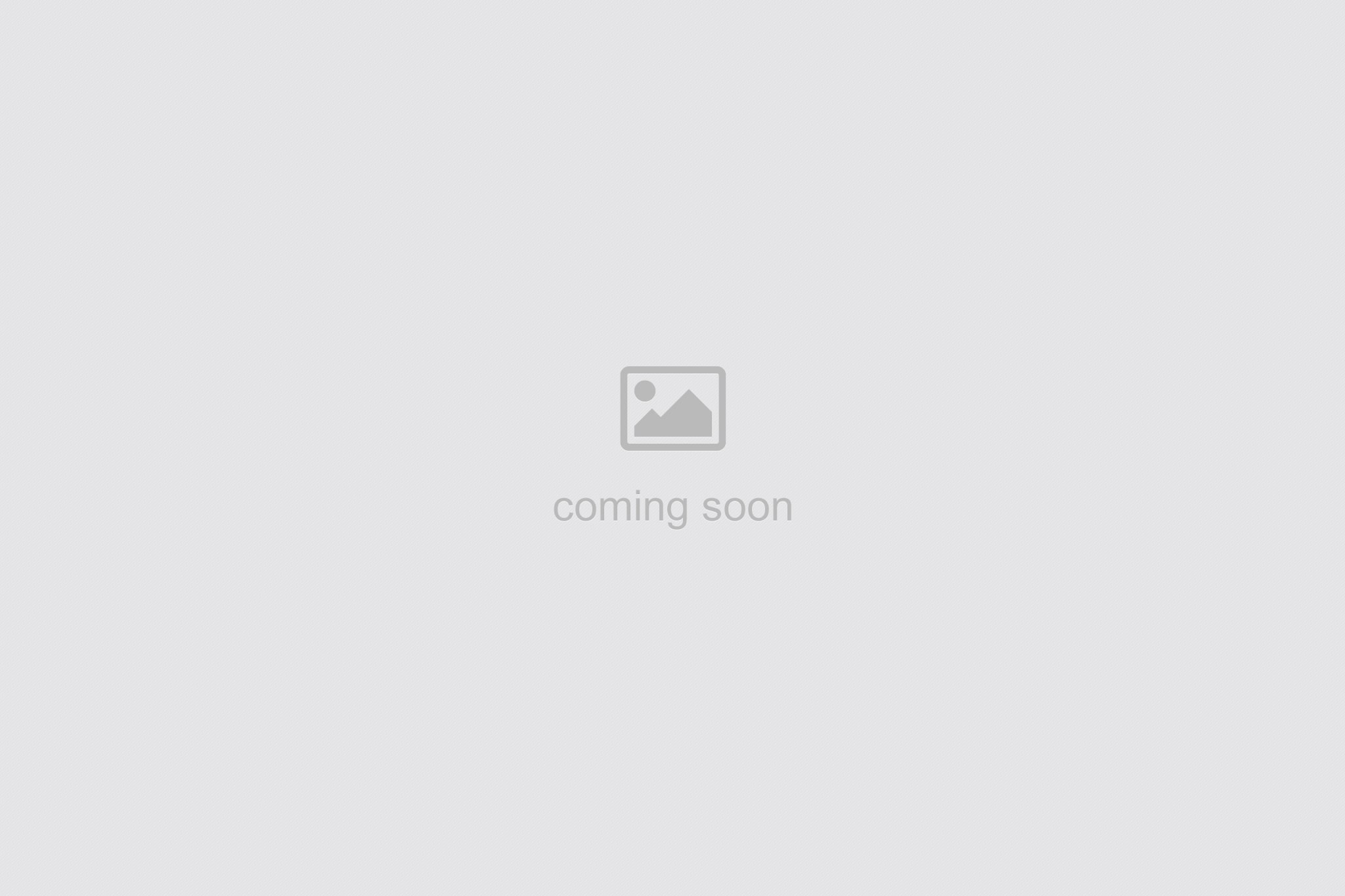栄養士コラム
第4号 ご飯は黄色? ~バランスの良い食事とは~
2021-09-17
よく「バランスの良い食事」と言いますが、このことを説明するときに赤、黄、緑の色を引き合いに使われる方も多いかと思います。
赤色の食品は「血や肉になるもの」で、代表的な食品は赤い肉や、魚、それにそれらから生み出される卵、乳製品、畑の牛肉と言われる大豆・大豆製品などです。
黄色の食品は「体を動かすもとになるもの」で、ご飯やパン、麺類などに代表される炭水化物、脂質などです。
緑色の食品は「体の調子を整えるもの」で、野菜類や海藻、きのこ類、果物などに含まれるビタミン類、ミネラル(無機質)類、食物繊維などです。
自動車に例えると、赤色は車の車体、黄色はガソリン・電気、緑はエンジンオイルやバッテリーなどメンテナンスに関わるものが当てはまります。どれ一つ欠けても快適に自動車を走らせることは出来ません。食事を摂る際に、これらの色のものをまんべんなく毎食食べてもらうことで、バランスの良い食事に近づくことになります。
外食では、黄色と赤色、黄色のみなどなって、緑色の食品のとり方が少なくなりがちです。足りない場合は緑色の食品を追加することで、バランス改善することが可能となります。
3色の色は皆さんも馴染みのある、信号の色です。青(緑)は進めですので、すすんで緑色の食品の摂取に心掛けたいです。
ご飯やパンや麺の色は「白色」なのに、なぜ黄色ですか?の問いかけには、米や小麦の収穫時には「黄金色」の実が実りますから黄色のイメージですよ、と答えております。
いよいよ富山自慢の新米の季節です。「実るほどこうべをたれる稲穂かな」のように実れば実るほど稲穂は垂れ下がります。私たちも謙虚に成長する稲穂に学びたいものですね。